2011年06月18日
蛍みてきました!
先週末の6月11日(土) 「箕面の生き物たち」~身近な生き物を通じて生物多様性にふれる~に
参加してきました。
第1部は、 お話と昆虫館見学で、箕面公園昆虫館/久留飛館長さんのお話を聞いたり、昆虫館の見学では生体展示にはしゃぐ子どもたち。
セアカフタマタクワガタ や ギラファノコギリクワガタ がいて、とまり木の下にかくれていたり、のぼっていたりと生体ごとの活動が見られて、おもしろかったです。
一見、止まり木の下に挟まっているように見えたので、そばにいた飼育員さんにお話を聞きましたら、
「生体より大きな止まり木でも、持ち上げてもぐりこんでいるのです。」とのこと。
わたくし、「へぇ~。」といいっぱなしでした。
また、ここではおなじみのゴキブリですが、ブラベルスのケースに居てる匹数にびっくりしましたが、飼育員さんはシェルターみたいなおうちをつくってあげてると聞いて、これまたびっくり。そういう話を聞くと、おもわずまたケースをみたり、見る角度が変わって、おもしろかったです。
第2部は、 ホタル観察会 (ゲンジホタル)
実際は日が暮れてから観察ですので、19:30以降の充分暗くなってから、見れます。
この日は駅周辺の場所。残念ながら路上駐車が多く、明るいと蛍が光ってくれません。
また、片道が路上駐車で埋まってしまってて、クラクションをならす車も多く、幻想的な観察とは
いきませんでした。
何年先も蛍を見続けれるように、マナーは守ってほしいものです。
蛍は最初の1匹が光りだすと、次々に光るということがわかりました。
確認でき始めると、周りから歓喜の声が!大人の方がはしゃいでたような・・・。
自由解散だったので、ずっとみてたいけど、20時過ぎには帰路につきました。
そしてうちならではの、もう一つのお楽しみ。
帰路の途中、いつものスーパーの横を通りながら、蛍の観察。3匹ほどは確認できました。
ゲンジホタル。
川の清掃で、ホタルの止まるところが少なく、確認しずらかったのかもしれません。
でも、でも、やっぱり、こんな手の届きそうな近くで観察できるなんて、
箕面人は幸せです。大切にしたいですね~。
参加してきました。
第1部は、 お話と昆虫館見学で、箕面公園昆虫館/久留飛館長さんのお話を聞いたり、昆虫館の見学では生体展示にはしゃぐ子どもたち。
セアカフタマタクワガタ や ギラファノコギリクワガタ がいて、とまり木の下にかくれていたり、のぼっていたりと生体ごとの活動が見られて、おもしろかったです。
一見、止まり木の下に挟まっているように見えたので、そばにいた飼育員さんにお話を聞きましたら、
「生体より大きな止まり木でも、持ち上げてもぐりこんでいるのです。」とのこと。
わたくし、「へぇ~。」といいっぱなしでした。
また、ここではおなじみのゴキブリですが、ブラベルスのケースに居てる匹数にびっくりしましたが、飼育員さんはシェルターみたいなおうちをつくってあげてると聞いて、これまたびっくり。そういう話を聞くと、おもわずまたケースをみたり、見る角度が変わって、おもしろかったです。
第2部は、 ホタル観察会 (ゲンジホタル)
実際は日が暮れてから観察ですので、19:30以降の充分暗くなってから、見れます。
この日は駅周辺の場所。残念ながら路上駐車が多く、明るいと蛍が光ってくれません。
また、片道が路上駐車で埋まってしまってて、クラクションをならす車も多く、幻想的な観察とは
いきませんでした。
何年先も蛍を見続けれるように、マナーは守ってほしいものです。
蛍は最初の1匹が光りだすと、次々に光るということがわかりました。
確認でき始めると、周りから歓喜の声が!大人の方がはしゃいでたような・・・。
自由解散だったので、ずっとみてたいけど、20時過ぎには帰路につきました。
そしてうちならではの、もう一つのお楽しみ。
帰路の途中、いつものスーパーの横を通りながら、蛍の観察。3匹ほどは確認できました。
ゲンジホタル。
川の清掃で、ホタルの止まるところが少なく、確認しずらかったのかもしれません。
でも、でも、やっぱり、こんな手の届きそうな近くで観察できるなんて、
箕面人は幸せです。大切にしたいですね~。
2010年10月06日
教学の森開設30周年記念イベント ブラジル流バーベキュー

教学の森開設30周年記念イベント 「家族で楽しむブラジル流バーベキュー」 が開催され、ブラジル流って何?どう違うの??と、興味津々で行って来ました。
場所は、箕面市立青少年教学の森野外活動センターです。ここはたどり着くまでに坂がきついですが、駐車場もあるので、小さい子連れでも比較的行きやすいのが嬉しいところです。
会場はブラジル国旗が飾られ、雰囲気も万全。下準備が進められていました。
今日のメニューは、

・牛肉の豪快岩塩焼き <ピーカンヤ(イチボのステーキ)とアウカトラ(ランプステーキ)と肉は2種類!>
・ブラジルソーセージのバーベキュー <リングウィッサ>
・ブラジルのお酢で味付けた手羽先のバーベキュー <フランゴ>
・トマトとキュウリ ブラジルマリネ風 <ヴィナグレッジ>
・ジャガイモとオリーブのマヨネーズサラダ <マヨネージサラダ>
です。
講師の方から、ブラジルでは毎週末にバーベキューをするほど機会がよくあることや、今日のメニューの紹介とこのお料理は日頃からよく食べているという説明がありました。

ジョゼ・アントニオ=マサル・タナカさん(左)、昌保英子さんご夫妻(右) ジョニードス=サントスさん(中央)


子どもたちはトマトやキュウリを切ったり、湯がいてあるジャガイモの皮をむいたり、つぶしたりしました。また料理を手伝った後、お肉を焼いている間は、どんぐりをひろったり、辺りを駆け回ったりして、各々とてもたのしそうでした。いろんなご家族が参加されていたのですが、子どもの年齢が2歳ぐらいから小学校低学年で、子どもはすぐにお友達になっていました。
ブラジルのお酢で味付けた手羽先のバーベキュー <フランゴ>は、1日漬け込んだほうが味がしみておいしいということで、前日から味付けしておいてくださったものです。


こどもたちでも自分たちで出来る料理があるくらい調理が簡単だったこと、味付けがシンプルなのですが講師の方が回って、味をみてくれたりしたので、どこのチームもうまく出来たようです。どれもとってもおいしい!!しかもたっぷりな量で、お腹もいっぱいになりました。

この日は食べ終わりごろから、雨が降り、予報よりはもってくれたもののあいにくのお天気で、山での散策は中止。しかしながら、急遽、講師の提案で、空手ボクササイズ&サンバ教室が開かれました。
講師の英子さんは日頃から、空手の講師をしておられ、ママ向けにも子ども同伴の空手ボクササイズもしておられる方です。
ひととおり、楽しく体を動かしたあとは、ティータイム。ブラジルのコンデンスミルクを使ったプリンと炭酸飲料やコーヒーなどを頂きながら、アントニオさんによるブラジルの母国語【ポルトガル語】講座で、盛り上がりました。ポルトガル語で自己紹介もしました!
おはようございます Bom dia ボン ヂーア
こんにちは! Ola'! 【オラ】
ありがとうを意味するObrigado オブリガードは知ってたのですが、これは男性言葉と言う事、女性はObrigada オブリガーダというのが正しいのだそうです。
閉所式には、全員の拍手喝采が沸き起こり、みなさん満足げな表情をされてました。
終わりには、こんなプレゼントも。

夫妻の温かい雰囲気と、教学の森のカウンセラーのみなさんのおかけでとても楽しい休日となりました。オブリガーダ!!
印象的だったのは、2児の父親であるアントニオさんが、「ブラジルではお父さんが育児に積極的に参加されるのが当たり前だよ。」と言いながら、終始、5歳の息子さんを抱っこしたり、サンバ教室の横でサッカーの相手をしたり、見事な育児ぶりでした。育メンとはこういうことをいうのですね。
(有光 いちか)
【情報】 教学の森開設30周年記念イベント 家族で楽しむブラジル流バーベキュー
対象…家族で参加できるかた(市外のかたも可)
日程…10月3日(日曜日)午前10時から午後3時
内容…肉をまるごと岩塩で焼くバーベキュー、ブラジル特産の酢で味付けた手羽先のバーベキューなど
講師…ジョゼ・アントニオ=マサル・タナカさん、昌保英子さんご夫妻 ジョニードス=サントスさん
定員…10家族(申込順)
持ち物…軍手
費用…小学生以上2000円、4歳以上の未就学児500円、3歳以下の幼児無料
2010年08月21日
箕面の山パトロール隊の夏休み 親子で虫を撮ろう!に参加

少し時間が経ってしまっているのですが・・・
今回は箕面の山パトロール隊の活動の大きな柱の一つ、
箕面の山の自然環境の保護を目的としたクリーンのつかないハイキング
「夏休み 親子で虫を撮ろう!」 に
家族の夏休みの楽しい行事として、参加させていただきました。
箕面の山パトロール隊とは、「箕面の山を美しくしたい」「箕面の山の美しさを子供たちに伝えていきたい」との思いから2004年8月に結成された団体さんです。(箕面の山パトロール隊ホームページより)
今回の目的は、虫を採ろう!ではなくて撮ろう!!です。
小学生以下の子どもを対象とし、デジカメ持参で撮りかたを教えてくださる・・・というもの。
教えてくださるのは、以前から素敵な写真を撮ることで、存じ上げていた谷上さんということで、おもわず私が飛びついたのでした。
この日は、とても暑く、クマゼミとアブラゼミがいっせいに鳴いてて、とっても大きな鳴き声でした。
セミや、抜け殻を観察しながら、現地まで歩いていると、水辺になにやら、発見。

ショウジョウトンボでした。
姉がトンボをもち、弟が写真撮影。

こちらはマメコガネ。
(撮影すべて:有光 いちか)

ニイニイゼミ

オオカマキリ(幼虫)

ウスバキトンボ


カマキリにバッタ、トンボ・・・と次々チャンスに出会うのですが、逃げられないか慌てて撮ってしまって、上記写真のように、ピントが当てたいところにあっていません。
アドバイスでは、
・ 昆虫の目にピントを合わせること。
・ とりあえず撮ってみて、逃げなかったらさらに寄ってみて撮影すること。
とのことで、サポートを受けながら、撮影しました。
個人的には、バッタのような、顔や体が細いものがピントを合わすのがとても難しかったです。
(その様子は、こちらでも見れます。→箕面の山パトロール隊ホームページへ)
ヤマトシジミ

ベニシジミ

上と同じ角度で、さらにアドバイス通りに寄ってみます。もう1枚撮影!

これが、本日のベストショットです!
これだけ寄れば、チョウチョの顔もわかるし、けっこう美人です。観察もより深くできるので、撮るのはいいですね。
なんだか1日で腕が上がったような気がする楽しい、気分爽やかなハイキングでした。
箕面の山パトロール隊みなさま、ありがとうございました。
【情報】
夏休み 親子で虫を撮ろう!
2010年7月31日(土) 午前10時~午後12時
白島バス停から徒歩5分ほどの原っぱ
主催 箕面の山パトロール隊
2010年01月06日
こどもと季節の行事を楽しもう
冬の大きな行事といえば、クリスマスとお正月。
少し前のお話になってしまって、申し訳ないのですが、2つのワークショップを体験してきました。
思い出深く、来年も楽しみたいと思いましたので、みなさんに紹介したいと思います。
まずは、クリスマスリース作りから。
みのおエコクラブのみなさんと箕面スパーガーデン1階で行いました。
用意してくださったのは、全て箕面の山で収穫したつるや杉、椿、ヒイラギ、千両、南天などです。松ぼっくりは、かなり大きいもので、棘がしっかりしていて痛いくらいです。
子ども達は、飾りを選ぶのに必死になってました。
つるはこの日に合わせて、3日前に命がけで採ってこられたそうです。この作業は、とってもハードなものだそうです。ありがたいです・・・。


まずは、土台のリース作り。
つるも、山葡萄、アケビ、など素材によって、雰囲気も変わります。当然固さも違いますので、アケビなんかは固く、ゆっくり曲げていかないと折れてしまいますし、なかなか思うようには行きません
そこがまた、夢中になって楽しめました。
うちは家族4人で参加させていただいたのですが、小1のムスメは、アケビでリースを作ってました。すこしゆるいのですが、自然の蔓の形を活かして巻いていると、なんとなく星型のリースが出来ました。


パパが作ったおうち型



ムスコも飾りつけしたリースがひとつ出来て、たくさんできたクリスマスリースでしたが、帰りに双方のおじいちゃん・おばあちゃんの所に届けに行って、クリスマスプレゼントになりました。
その3日後、年の瀬も迫ったということで、市民活動センターで行われた手作り名人 後藤さんによる 『 注連縄作り 』 に参加しました。今回はみっけメンバーと一緒の参加です。


見本を見ながら、後ろの飾りの凧を作りました。そしていよいよ注連縄作り。
手でわら(この日はいぐさ)をよるのが、後藤さんはなれておられるので早いのですが、小さい手ではよるのも難しかったです。小学校3年生ぐらいの子どもさんだと自分で出来てました。



みなさん、後藤さんに手伝ってもらいながら、進めているところ、雪国育ちのみっけメンバーの一人は、すごく手馴れた様子でこなしていました。聞くと、子どものときからわら草履とか編むことがあったそう。うらやましい・・・。
最初は、出来ないムスメを手伝っていたつもりの私でしたが、
3つに分けたうちの2本をよって、絡めたら、残りの1本を布を巻きつけながら、絡めていくのですが、ここでやり方がわかっておらず間違ったため、作り直すもボロボロで、結局、後藤さんに手伝ってもらいました。

出来た注連縄を、凧と組み合わせて、飾りの葉や木の実を思い思いにつけて、あとはおめでたい言葉を書いたピックをさせば、出来上がり。
みなさん、どの言葉にするか悩んでいて、初春とか、立春とか、寿など、一筆一筆想いをこめて、書かれてました。
後藤さんの作品は、きりっと編まれていて、市民活動センターの出入り口のところで、販売もされてました。

これから親子で楽しむ季節といえば、節分でしょうか。豆を撒いた後が大変なのですが、子どもたちの好きな行事です。
節分(せつぶん、またはせちぶん)は、各季節の始まりの日(立春・立夏・立秋・立冬)の前日のこと。節分とは「季節を分ける」ことをも意味しているそうです。特に江戸時代以降は立春(毎年2月3日ごろ、うるう年は2月4日ごろ)の前日に、
豆を撒き、撒かれた豆を、自分の年齢(数え年)の数だけ食べる。また、自分の年の数の1つ多く食べると、体が丈夫になり、風邪をひかないというならわしがあります。
最近は、豆が小袋に入っていて、小袋ごと撒けるのもありますし、鬼がいる家いない家、どちらも大きな声で「福は内~、鬼は外~。」と撒けば、寒さも吹っ飛び、1年元気でいられそうです。
我が家では、翌日朝早くから、たくさんのすずめがやってきて起こされるのも、この行事のご愛嬌です。
ぜひ、みなさんも試してみてくださいね。
行事を楽しむポイントは、『自己流』なんじゃないかと思います。
子どもたちと我が家ならではの、オリジナルってとこに、うまく行かなくっても楽しい! うまく行けばさらに楽しい! という思い出が、温かい気持ちとなって残ります。
そういう体験をした子どもは、自分が大人になったときにも必ず思い出すのだそうです。
形よりも、行事をたのしむそのときの気持ち。 とっても大事なことですね。
( 有光 いちか )
少し前のお話になってしまって、申し訳ないのですが、2つのワークショップを体験してきました。
思い出深く、来年も楽しみたいと思いましたので、みなさんに紹介したいと思います。
まずは、クリスマスリース作りから。
みのおエコクラブのみなさんと箕面スパーガーデン1階で行いました。
用意してくださったのは、全て箕面の山で収穫したつるや杉、椿、ヒイラギ、千両、南天などです。松ぼっくりは、かなり大きいもので、棘がしっかりしていて痛いくらいです。
子ども達は、飾りを選ぶのに必死になってました。
つるはこの日に合わせて、3日前に命がけで採ってこられたそうです。この作業は、とってもハードなものだそうです。ありがたいです・・・。


まずは、土台のリース作り。
つるも、山葡萄、アケビ、など素材によって、雰囲気も変わります。当然固さも違いますので、アケビなんかは固く、ゆっくり曲げていかないと折れてしまいますし、なかなか思うようには行きません

そこがまた、夢中になって楽しめました。
うちは家族4人で参加させていただいたのですが、小1のムスメは、アケビでリースを作ってました。すこしゆるいのですが、自然の蔓の形を活かして巻いていると、なんとなく星型のリースが出来ました。


パパが作ったおうち型



ムスコも飾りつけしたリースがひとつ出来て、たくさんできたクリスマスリースでしたが、帰りに双方のおじいちゃん・おばあちゃんの所に届けに行って、クリスマスプレゼントになりました。
その3日後、年の瀬も迫ったということで、市民活動センターで行われた手作り名人 後藤さんによる 『 注連縄作り 』 に参加しました。今回はみっけメンバーと一緒の参加です。


見本を見ながら、後ろの飾りの凧を作りました。そしていよいよ注連縄作り。
手でわら(この日はいぐさ)をよるのが、後藤さんはなれておられるので早いのですが、小さい手ではよるのも難しかったです。小学校3年生ぐらいの子どもさんだと自分で出来てました。



みなさん、後藤さんに手伝ってもらいながら、進めているところ、雪国育ちのみっけメンバーの一人は、すごく手馴れた様子でこなしていました。聞くと、子どものときからわら草履とか編むことがあったそう。うらやましい・・・。
最初は、出来ないムスメを手伝っていたつもりの私でしたが、
3つに分けたうちの2本をよって、絡めたら、残りの1本を布を巻きつけながら、絡めていくのですが、ここでやり方がわかっておらず間違ったため、作り直すもボロボロで、結局、後藤さんに手伝ってもらいました。

出来た注連縄を、凧と組み合わせて、飾りの葉や木の実を思い思いにつけて、あとはおめでたい言葉を書いたピックをさせば、出来上がり。
みなさん、どの言葉にするか悩んでいて、初春とか、立春とか、寿など、一筆一筆想いをこめて、書かれてました。
後藤さんの作品は、きりっと編まれていて、市民活動センターの出入り口のところで、販売もされてました。

これから親子で楽しむ季節といえば、節分でしょうか。豆を撒いた後が大変なのですが、子どもたちの好きな行事です。
節分(せつぶん、またはせちぶん)は、各季節の始まりの日(立春・立夏・立秋・立冬)の前日のこと。節分とは「季節を分ける」ことをも意味しているそうです。特に江戸時代以降は立春(毎年2月3日ごろ、うるう年は2月4日ごろ)の前日に、
豆を撒き、撒かれた豆を、自分の年齢(数え年)の数だけ食べる。また、自分の年の数の1つ多く食べると、体が丈夫になり、風邪をひかないというならわしがあります。
最近は、豆が小袋に入っていて、小袋ごと撒けるのもありますし、鬼がいる家いない家、どちらも大きな声で「福は内~、鬼は外~。」と撒けば、寒さも吹っ飛び、1年元気でいられそうです。
我が家では、翌日朝早くから、たくさんのすずめがやってきて起こされるのも、この行事のご愛嬌です。
ぜひ、みなさんも試してみてくださいね。
行事を楽しむポイントは、『自己流』なんじゃないかと思います。
子どもたちと我が家ならではの、オリジナルってとこに、うまく行かなくっても楽しい! うまく行けばさらに楽しい! という思い出が、温かい気持ちとなって残ります。
そういう体験をした子どもは、自分が大人になったときにも必ず思い出すのだそうです。
形よりも、行事をたのしむそのときの気持ち。 とっても大事なことですね。
( 有光 いちか )
2009年10月23日
箕面の伝統 秋の天狗まつり
歴史ある箕面の伝統行事について、書きたいと思います。
毎年10月15・16日には聖天宮秋季大祭の「天狗まつり」が開催されます。15日夜に宵宮、16日昼に悪魔払い、16日夜に本宮が行なわれます。祭りの起源は定かではないですが、江戸時代末期にはその様子を記したものが残っています。
からす天狗、役行者(えんのぎょうじゃ)、猿田彦など日本の天狗伝説は彼らによるものが多く、その大半は役行者に由来するといわれ、聖天宮西江寺の天狗も役行者が変化したものだそうです。
祭りは祭礼委員会と地元の消防団員有志によって行われ、宵宮と本宮の夜は境内に響く太鼓の音と掛け声に合わせ天狗と神楽(獅子舞)が踊ります。「やらまい!!」の掛け声は「やれ舞え、それ舞え!」が起源。天狗や神楽が子どもを追いかけて叩くのは邪気祓い・悪魔払いの意味があり、天狗に叩かれると元気で賢い子に育つ、女性はお尻を叩かれると子宝に恵まれるといわれています。
昼は神楽と天狗が地域の家々を回り、お祓いを行います。天狗まつりは「無病息災」「子孫繁栄」を願う祭りです。
16日朝は、西江寺さんに近い幼稚園や小学校にも、神楽と天狗が来てくれて、お祓いをしてくれます。小学校には、近くの保育所・幼稚園年長児の子どもたちも来て、交流会にもなっています。
こどもたちは、震え上がり泣き出す子、好奇心旺盛に天狗に近づく子とさまざまです。




走るとすごく速いんです。

簓(ささら)と簓子(ささらこ)をすり合わせ、狙いをつけてます。

近くにきた!!
(おもわず逃げましたので、走ってる勇姿は撮影できず。恐ろしくて震え上がりました )
)



夜、太鼓の音が鳴り響く境内で、天狗は簓(ささら)と簓子(ささらこ)をすり合わせながら走り回り、つぎつぎと人々の頭をたたきまわります。簓(ささら)とは、竹の先を細かく割いて、叩かれたこどもたちが怪我をしないようにしてあるのですが、真剣に叩かれるとそれでも痛いです。
聖天宮西江寺(せいてんぐうさいこうじ)の天狗まつりのことを中心に書きましたが、実は天狗まつりは、聖天宮西江寺(箕面2丁目)と西小路八幡太神社(にししょうじはちまんたじんじゃ)の二カ所で開催されます。 (開催日時も、違います)
根っからの箕面人の私は、幼少のころは、西小路に住んでおり、1日目に八幡太神社の天狗と神楽(獅子舞)が家に訪ねてくるので、いつくるか、いつくるかとドキドキしながら震え上がり、家の人形やぬいぐるみを飾ってある棚に、同化して並び、声をひそめたものです。(もちろん天狗や神楽(獅子舞)は、家の中までは入ってきません。)子供心に、子供がいる家だとわかると探しに入ってきそうだと思ったからです。本来、天狗に叩かれると元気で賢い子に育つ。神楽(獅子舞)にかまれると病気せず、賢くなるというのに、あまりに怖い風貌、下駄の音さえこわかった覚えがあります。
そんなに怖がっていた私でも、小学生になると、怖いながらも西小路のおおよそ1本道で行われる天狗まつりを見に出かけていったものです。広くない道路の端は見物する人ばかりなのですが、天狗を挑発した人が叩かれそうになって逃げてきたり、お酒を飲んでいる天狗が暴走したりして、巻き込まれる可能性もあるので、気は抜けません。民家の塀の壁に体をこすりつけながら、見物してました。
また、獅子舞も歯をガチガチ鳴らしながら、近づいて来て、手にはしっかり簓(ささら)が握られ、叩かれます。
当時私たちの間では黒天狗(通称ブラックと呼ばれてました。)が最強とされ、黄ぃカッパは、下っ端の天狗といちづけされていたような気がします。足の速さとか、叩きの強さとかでこども達が決めていたと思います。
あの簓(ささら)を地面や壁にこすって走ってくる姿は(やっぱり中腰 )、迫力満点でした。お酒を飲みすぎて、こけて面を割って(鼻を折って)しまった天狗もいてましたし・・・。(現在は、お酒もセーブされているようです。)
)、迫力満点でした。お酒を飲みすぎて、こけて面を割って(鼻を折って)しまった天狗もいてましたし・・・。(現在は、お酒もセーブされているようです。)
お酒を飲んでいるとか、子供たちをしばいている様子が、知らない人から見れば暴力的で乱暴な祭りに見えるかもしれませんが、 あきらかに無礼な挑発をしてくる子供にはしばいているぐらいで、本来は今も昔も変わらず、邪気祓い・悪魔払いで災いを拭ってもらい、健やかに育つ事を望む大人たちの願いと祈りが『祭り』となったもので、このお祭りをささえる地域の人たちの温かさがあってこそ、成り立つ行事なのです。
大人になってよかったなと思うのは、お祭りにかかさず参加していた子ども時代より、運営している地域の人たちの気持ちに近づいた今のほうが、いろいろ見えてきて、面白みも増えたような気がします。
地域のお神輿(おみこし)やお祭りは、その地域の子供会や自治会が行っていることが多いのですが、小さい子どもさんを喜んで参加させてくれる地域の人たちもいます。どうしたら参加することができるのか、ご近所の方やお祭りの日に周りの人に聞いてもらいたいです。ぜひ、みなさんもそれぞれの地域のお祭りに参加してみてください。
(有光 いちか)

【情報】 *2009年の日程を記録として記載
箕面市内の秋祭り
■八幡太神社(箕面市新稲3-6-1)
10月3日(土) 午前8時~ 子ども神輿、天狗が西小路地域を巡行
■為那都比古神社(箕面市石丸2-10-1 TEL072-729-7045)
10月14日(水) 午前10時~ 献灯の儀 、午後1時~5時 かぐら奉納
■牧落八幡大神宮(箕面市牧落2-12-27 TEL072-724-2218)
10月17日(土) 午後4時~8時 前夜祭・森のコンサートほか
10月18日(日) 午前8時~午後7時 子ども太鼓、子ども神輿などの巡行
10月22日(木) 午前10時~ 祭典
■下止々呂美 だんじり祭り
10月17日(土) 午後4時~ だんじり巡航
10月18日(日) 午前8時30分~ だんじり巡航
■阿比太神社(箕面市桜ヶ丘1-8-1 TEL072-721-2096)
10月18日(日) 午前10時30分~ 祭典、正午~午後4時 神輿巡行
■春日神社(箕面市小野原西5-3-11 TEL072-722-3760)
10月18日(日) 午前9時~ 式典、神楽
■素盞嗚尊神社(箕面市粟生間谷2912番地)
10月18日(日) 午前8時~ 式典、太鼓巡行
■瀬川神社(箕面市瀬川1-22-20 TEL072-722-1207)
10月25日(日) 午前10時~午後3時 祭典

毎年10月15・16日には聖天宮秋季大祭の「天狗まつり」が開催されます。15日夜に宵宮、16日昼に悪魔払い、16日夜に本宮が行なわれます。祭りの起源は定かではないですが、江戸時代末期にはその様子を記したものが残っています。
からす天狗、役行者(えんのぎょうじゃ)、猿田彦など日本の天狗伝説は彼らによるものが多く、その大半は役行者に由来するといわれ、聖天宮西江寺の天狗も役行者が変化したものだそうです。
祭りは祭礼委員会と地元の消防団員有志によって行われ、宵宮と本宮の夜は境内に響く太鼓の音と掛け声に合わせ天狗と神楽(獅子舞)が踊ります。「やらまい!!」の掛け声は「やれ舞え、それ舞え!」が起源。天狗や神楽が子どもを追いかけて叩くのは邪気祓い・悪魔払いの意味があり、天狗に叩かれると元気で賢い子に育つ、女性はお尻を叩かれると子宝に恵まれるといわれています。
昼は神楽と天狗が地域の家々を回り、お祓いを行います。天狗まつりは「無病息災」「子孫繁栄」を願う祭りです。
16日朝は、西江寺さんに近い幼稚園や小学校にも、神楽と天狗が来てくれて、お祓いをしてくれます。小学校には、近くの保育所・幼稚園年長児の子どもたちも来て、交流会にもなっています。
こどもたちは、震え上がり泣き出す子、好奇心旺盛に天狗に近づく子とさまざまです。




走るとすごく速いんです。

簓(ささら)と簓子(ささらこ)をすり合わせ、狙いをつけてます。

近くにきた!!
(おもわず逃げましたので、走ってる勇姿は撮影できず。恐ろしくて震え上がりました
 )
)
賢くなりますように~


この中腰姿が、異様にやたらと恐ろしい。
子どもに合わせて中腰になっているのですが、大人になってもびびらされるものが・・・。
簓(ささら)と簓子(ささらこ)をすり合わせて、おどされます。
(あまりの迫力に、これが精一杯よったときです。やっぱり怖くて近寄れませんでした・・・。)
子どもに合わせて中腰になっているのですが、大人になってもびびらされるものが・・・。
簓(ささら)と簓子(ささらこ)をすり合わせて、おどされます。
(あまりの迫力に、これが精一杯よったときです。やっぱり怖くて近寄れませんでした・・・。)
夜、太鼓の音が鳴り響く境内で、天狗は簓(ささら)と簓子(ささらこ)をすり合わせながら走り回り、つぎつぎと人々の頭をたたきまわります。簓(ささら)とは、竹の先を細かく割いて、叩かれたこどもたちが怪我をしないようにしてあるのですが、真剣に叩かれるとそれでも痛いです。
聖天宮西江寺(せいてんぐうさいこうじ)の天狗まつりのことを中心に書きましたが、実は天狗まつりは、聖天宮西江寺(箕面2丁目)と西小路八幡太神社(にししょうじはちまんたじんじゃ)の二カ所で開催されます。 (開催日時も、違います)
根っからの箕面人の私は、幼少のころは、西小路に住んでおり、1日目に八幡太神社の天狗と神楽(獅子舞)が家に訪ねてくるので、いつくるか、いつくるかとドキドキしながら震え上がり、家の人形やぬいぐるみを飾ってある棚に、同化して並び、声をひそめたものです。(もちろん天狗や神楽(獅子舞)は、家の中までは入ってきません。)子供心に、子供がいる家だとわかると探しに入ってきそうだと思ったからです。本来、天狗に叩かれると元気で賢い子に育つ。神楽(獅子舞)にかまれると病気せず、賢くなるというのに、あまりに怖い風貌、下駄の音さえこわかった覚えがあります。
そんなに怖がっていた私でも、小学生になると、怖いながらも西小路のおおよそ1本道で行われる天狗まつりを見に出かけていったものです。広くない道路の端は見物する人ばかりなのですが、天狗を挑発した人が叩かれそうになって逃げてきたり、お酒を飲んでいる天狗が暴走したりして、巻き込まれる可能性もあるので、気は抜けません。民家の塀の壁に体をこすりつけながら、見物してました。
また、獅子舞も歯をガチガチ鳴らしながら、近づいて来て、手にはしっかり簓(ささら)が握られ、叩かれます。
当時私たちの間では黒天狗(通称ブラックと呼ばれてました。)が最強とされ、黄ぃカッパは、下っ端の天狗といちづけされていたような気がします。足の速さとか、叩きの強さとかでこども達が決めていたと思います。
あの簓(ささら)を地面や壁にこすって走ってくる姿は(やっぱり中腰
 )、迫力満点でした。お酒を飲みすぎて、こけて面を割って(鼻を折って)しまった天狗もいてましたし・・・。(現在は、お酒もセーブされているようです。)
)、迫力満点でした。お酒を飲みすぎて、こけて面を割って(鼻を折って)しまった天狗もいてましたし・・・。(現在は、お酒もセーブされているようです。)お酒を飲んでいるとか、子供たちをしばいている様子が、知らない人から見れば暴力的で乱暴な祭りに見えるかもしれませんが、 あきらかに無礼な挑発をしてくる子供にはしばいているぐらいで、本来は今も昔も変わらず、邪気祓い・悪魔払いで災いを拭ってもらい、健やかに育つ事を望む大人たちの願いと祈りが『祭り』となったもので、このお祭りをささえる地域の人たちの温かさがあってこそ、成り立つ行事なのです。
大人になってよかったなと思うのは、お祭りにかかさず参加していた子ども時代より、運営している地域の人たちの気持ちに近づいた今のほうが、いろいろ見えてきて、面白みも増えたような気がします。
地域のお神輿(おみこし)やお祭りは、その地域の子供会や自治会が行っていることが多いのですが、小さい子どもさんを喜んで参加させてくれる地域の人たちもいます。どうしたら参加することができるのか、ご近所の方やお祭りの日に周りの人に聞いてもらいたいです。ぜひ、みなさんもそれぞれの地域のお祭りに参加してみてください。
(有光 いちか)

【情報】 *2009年の日程を記録として記載
箕面市内の秋祭り
■八幡太神社(箕面市新稲3-6-1)
10月3日(土) 午前8時~ 子ども神輿、天狗が西小路地域を巡行
■為那都比古神社(箕面市石丸2-10-1 TEL072-729-7045)
10月14日(水) 午前10時~ 献灯の儀 、午後1時~5時 かぐら奉納
■牧落八幡大神宮(箕面市牧落2-12-27 TEL072-724-2218)
10月17日(土) 午後4時~8時 前夜祭・森のコンサートほか
10月18日(日) 午前8時~午後7時 子ども太鼓、子ども神輿などの巡行
10月22日(木) 午前10時~ 祭典
■下止々呂美 だんじり祭り
10月17日(土) 午後4時~ だんじり巡航
10月18日(日) 午前8時30分~ だんじり巡航
■阿比太神社(箕面市桜ヶ丘1-8-1 TEL072-721-2096)
10月18日(日) 午前10時30分~ 祭典、正午~午後4時 神輿巡行
■春日神社(箕面市小野原西5-3-11 TEL072-722-3760)
10月18日(日) 午前9時~ 式典、神楽
■素盞嗚尊神社(箕面市粟生間谷2912番地)
10月18日(日) 午前8時~ 式典、太鼓巡行
■瀬川神社(箕面市瀬川1-22-20 TEL072-722-1207)
10月25日(日) 午前10時~午後3時 祭典
2009年08月10日
ダンボールキャンプ
みのおエコクラブ主催のダンボールキャンプ(1泊2日)に参加してきました。
朝、集合時間からあいにくのお天気。でも、雨でも大丈夫なように場所の確保とスケジュールをプランニングしてくださっているので、安心。
まずは、オリエンテーション。班分けとリーダーの確認。
去年も参加された家族が、リーダーに任命されてました。
それと、エコクラブのルールの説明がありました。
『子どもが転んでも起こさないで見てる。』 危ない事以外は、とにかく様子を見るのです。
そして、 『役割をまもる。』 小さい子にも小さいなりにできる役割が与えられます。
それと 『無駄にしない。再利用する。』 1杯のバケツで、数人が手を洗いますが、水を汚さない手の洗い方があるのです。手で、バケツの水をすくって外に出して、バケツの外で洗うと、1人目でバケツの水全部が汚れてしまうことを防げます。
いざ、屋根はあるけど野外なところに、班のメンバーと村をつくって、各自ダンボールハウスを設営。形も大きさも思い思いに作っていきます。
テント式のところ、フルオープンで茶室のようにつくっているところ、個性豊かです。
我が家は、家族でひとつのワンルームで作っていたら、家族全員が個室があるおうちもありました。
昼食と自由時間をはさんで、休憩したら、畑の手入れと、夕食のカレー作り、子供たちは竹とんぼを飛ばしたり、風車工作と、担当ごとに分かれて活動。
この場所は、野外とはいえど焚き火はできないので、カセットコンロを使っての調理に変更。少し早目から夕食準備にかかり、後のお楽しみを早めることに。
夕食のメニューはカレー。ご飯は飯盒炊飯です。
飯ごう炊飯はやり方をおしえてもらいますが、失敗した班はご飯がなくなり、カレーだけになるため、やるほうも必死です。風除けを自分たちで作りながら、あ~でもないこ~でもないと真剣。自然にコミュニケーションが生まれます。
カレーの材料は、エコクラブで用意してくださったもの。おいしい品種のジャガイモに、サツマイモ、カボチャ、タマネギ、そして、苦手な子が多いピーマンを細かく刻んでいれました。これも、食べれないと言う子にチャレンジさせるためだったのですが、ニンニクが隠し味のカレーは大変おいしく出来上がり、ピーマンがイヤだと言う子はいませんでした。(気づかなかった?)
担当のカレーがおおよそ出来上がって、飯ごう炊飯の応援に出た私でしたが、沸騰したか?炊き上がったか?を音と匂いで嗅ぎ分けなければならないため、「焦がしたかも~っ!!」と内心半泣きで、蒸らしたご飯は、意外と上手に炊けてて、ホッとしました。
大成功のカレーライスに、みなさん、おかわりしたり、ほお張っていました。大成功の喜びで、おいしさもひとしおだったのだと思います。
夕食後、お風呂に入り、PLの花火を見ながら、大人は飲みながら談笑し、子供は花火に夢中でした。
そして、ダンボールで就寝。雨が降っていたこともあって、夏でも長袖長ズボン着ても、寒いくらいでした。
やはりキャンプでは、荷物になっても、防寒具やナイロン素材のものを用意しとくべきだなと、実感しました。
翌日は、すいか割り&竹とんぼ飛ばし大会。
すいかは、小さい子どもたちの奮闘する姿がかわいかったですが、なかなか割れず、中学生のお兄ちゃんが大活躍しました。
子供たちは、昨日の練習のせいもあってか、大興奮で、みな上位を狙うつもりでいました。
それに感化されてか、だんだん大人たちも、本気で悔しがる様子が見られ、次こそは!!と意気込みすら感じられ、楽しかったです。勝った人には、景品があったのですが、2回戦であきらめがちに飛ばした私のがよく飛び、見事、景品をもらいました~。
この後、熱い熱気に耐えながら、男性陣が湯がいてくれたそうめんを食べて、お風呂に入って、解散となりました。
代表者の佐藤さんは、環境のことを考えて、子供たちに伝える。という方法をみんなに教えてくれる、きびしいけどとっても愛情が深い、昔ながらの近所のおじちゃんでした。
今時そういう存在が、私たちにとっても、子供たちにとっても、貴重でありがたいです。
(有光 いちか)
【情報】
ダンボールでマイハウスを造って泊まります。ハンゴウすいさん・カレー作り・スイカ割り・流しそうめん・竹とんぼ飛ばし等もあります。
日時: 8/1(土) 10:00~ 8/2(日) 15:00解散予定
会場: 箕面温泉スパーガーデン第2駐車場 (雨天時は館内)
集合: 9:30に箕面温泉スパーガーデン フロント前
参加費: 会員/ 保護者3,500円、子供3,000円 (5歳未満1,500円)
非会員/ 入会金1,000円をお願いします。
(温泉入浴料、食材、保険料、駐車料、ホテルバイキングの朝食を含みます)
【申込み】 072-724-6203 (みのおエコクラブ代表 佐藤) ※先着50名
主催: みのおエコクラブ
協力: 箕面温泉スパーガーデン
朝、集合時間からあいにくのお天気。でも、雨でも大丈夫なように場所の確保とスケジュールをプランニングしてくださっているので、安心。
まずは、オリエンテーション。班分けとリーダーの確認。
去年も参加された家族が、リーダーに任命されてました。
それと、エコクラブのルールの説明がありました。
『子どもが転んでも起こさないで見てる。』 危ない事以外は、とにかく様子を見るのです。
そして、 『役割をまもる。』 小さい子にも小さいなりにできる役割が与えられます。
それと 『無駄にしない。再利用する。』 1杯のバケツで、数人が手を洗いますが、水を汚さない手の洗い方があるのです。手で、バケツの水をすくって外に出して、バケツの外で洗うと、1人目でバケツの水全部が汚れてしまうことを防げます。
いざ、屋根はあるけど野外なところに、班のメンバーと村をつくって、各自ダンボールハウスを設営。形も大きさも思い思いに作っていきます。
テント式のところ、フルオープンで茶室のようにつくっているところ、個性豊かです。

我が家は、家族でひとつのワンルームで作っていたら、家族全員が個室があるおうちもありました。

昼食と自由時間をはさんで、休憩したら、畑の手入れと、夕食のカレー作り、子供たちは竹とんぼを飛ばしたり、風車工作と、担当ごとに分かれて活動。
この場所は、野外とはいえど焚き火はできないので、カセットコンロを使っての調理に変更。少し早目から夕食準備にかかり、後のお楽しみを早めることに。
夕食のメニューはカレー。ご飯は飯盒炊飯です。
飯ごう炊飯はやり方をおしえてもらいますが、失敗した班はご飯がなくなり、カレーだけになるため、やるほうも必死です。風除けを自分たちで作りながら、あ~でもないこ~でもないと真剣。自然にコミュニケーションが生まれます。
カレーの材料は、エコクラブで用意してくださったもの。おいしい品種のジャガイモに、サツマイモ、カボチャ、タマネギ、そして、苦手な子が多いピーマンを細かく刻んでいれました。これも、食べれないと言う子にチャレンジさせるためだったのですが、ニンニクが隠し味のカレーは大変おいしく出来上がり、ピーマンがイヤだと言う子はいませんでした。(気づかなかった?)
担当のカレーがおおよそ出来上がって、飯ごう炊飯の応援に出た私でしたが、沸騰したか?炊き上がったか?を音と匂いで嗅ぎ分けなければならないため、「焦がしたかも~っ!!」と内心半泣きで、蒸らしたご飯は、意外と上手に炊けてて、ホッとしました。
大成功のカレーライスに、みなさん、おかわりしたり、ほお張っていました。大成功の喜びで、おいしさもひとしおだったのだと思います。
夕食後、お風呂に入り、PLの花火を見ながら、大人は飲みながら談笑し、子供は花火に夢中でした。
そして、ダンボールで就寝。雨が降っていたこともあって、夏でも長袖長ズボン着ても、寒いくらいでした。
やはりキャンプでは、荷物になっても、防寒具やナイロン素材のものを用意しとくべきだなと、実感しました。
翌日は、すいか割り&竹とんぼ飛ばし大会。
すいかは、小さい子どもたちの奮闘する姿がかわいかったですが、なかなか割れず、中学生のお兄ちゃんが大活躍しました。
子供たちは、昨日の練習のせいもあってか、大興奮で、みな上位を狙うつもりでいました。
それに感化されてか、だんだん大人たちも、本気で悔しがる様子が見られ、次こそは!!と意気込みすら感じられ、楽しかったです。勝った人には、景品があったのですが、2回戦であきらめがちに飛ばした私のがよく飛び、見事、景品をもらいました~。
この後、熱い熱気に耐えながら、男性陣が湯がいてくれたそうめんを食べて、お風呂に入って、解散となりました。
代表者の佐藤さんは、環境のことを考えて、子供たちに伝える。という方法をみんなに教えてくれる、きびしいけどとっても愛情が深い、昔ながらの近所のおじちゃんでした。
今時そういう存在が、私たちにとっても、子供たちにとっても、貴重でありがたいです。
(有光 いちか)
【情報】
ダンボールでマイハウスを造って泊まります。ハンゴウすいさん・カレー作り・スイカ割り・流しそうめん・竹とんぼ飛ばし等もあります。
日時: 8/1(土) 10:00~ 8/2(日) 15:00解散予定
会場: 箕面温泉スパーガーデン第2駐車場 (雨天時は館内)
集合: 9:30に箕面温泉スパーガーデン フロント前
参加費: 会員/ 保護者3,500円、子供3,000円 (5歳未満1,500円)
非会員/ 入会金1,000円をお願いします。
(温泉入浴料、食材、保険料、駐車料、ホテルバイキングの朝食を含みます)
【申込み】 072-724-6203 (みのおエコクラブ代表 佐藤) ※先着50名
主催: みのおエコクラブ
協力: 箕面温泉スパーガーデン
2009年07月20日
里山体験その後

いただいた笹はこんなに大きかったのです。
立派でしょう~?
奥には、毎年恒例の幼稚園からいただく笹。これも相当立派なのですが、今年は、ダブルで大作でした。
2009年07月20日
教学の森で、アウトドアも楽しもう!
家族でアウトドアやキャンプをするのって、楽しいけど、準備も多いし、料理を作りながら、火をみて、子どもたちが怪我をしないように見てるのが、大変!そこで、みっけ!からの提案は、何家族かで行くこと!
そのときに、パパにもぜひにって、参加してもらったほうが、うまくいきます。やっぱり外ではパパの出番が多くなりますからね。
パパにも育児の話や、趣味の話が出来るパパ友達をつくるチャンスだし、みんなで分担すれば、家族の中でパパだけが働きっぱなし(!)にもならなくて済むのでは?
料理は何でもいいけれど、簡単で、子どもたちも料理に参加しやすいカレーライスとバーベキューにしました。どちらも王道ですよね。
なぜ、どちらも?と思われた方もおられるのではないでしょうか。はい、どちらかでもいいのですが、カレーは子ども受けがよく、バーベキューは大人受けがいいからです。まずは、カレーライスを作ってしまって、子供たちは基本的にはカレーライスが昼食です。あとから、ゆっくりバーベキューをしても、充分です。

今回は、洗ったお米とカレーの具材、バーベキューの具材を、各家庭分は各自で持ち寄りで、
カレールウ(甘口を用意しました)や、この甘口のカレーに、大人向けの辛さにできるスパイス(食べるときに入れる)と、バーベキュー用の焼肉たれなどは、まとめて購入しました。
最初は、自分の子どもに教えていましたが、自然とだんだん他の子に教えてたりします。一緒のことをみんなでする醍醐味ですね。


カレーとは言えど、具材の打ち合わせもなく、お楽しみのごった煮です。お肉も牛だったり、チキンだったり、豚肉だったり・・・。
でもでも、とっても、おいしかったんです。
みんなすごくおかわりして、まずご飯がなくなった!!子どもたちよく食べる、食べる。
ルウはさらっとした食感で、マイルドな味だったし、大人はカレースープとして飲んでたりもしました。

コツは、早く火が通るように、野菜もお肉もいつもよりずっとずっと細かく切ること。
これで、具材が固い!というよくありがちなことは、防げました。また、今回のように、カレールウがあまった場合に持って帰れるように、ファスナーつきジップロックを用意してると、ご飯も野菜でもなんでも捨てなくて済みます。
この場所を選んだのは、近いからだけではなく、キャンプカウンセラーのお兄さんやお姉さんが、いてくれるからです。
道具の準備、火の起こし方、飯ごう炊飯の仕方、など、わからないことは教えてくださるので、頼もしいです。また、子どもたちが午後から連れて行ってもらったグリーンハイキングは、きのこや虫をみつけたり、クイズをしてもらったり、とっても楽しかったそうです。
また、ベビー連れだったのですが、木陰がありますし、思ったより快適にベビーカーで寝ていました。
これから秋まで、楽しめると思いますので、ぜひトライしてみてくださいね。
この日は、みっけ!みのおの子連れアウトドアの様子を
タッキー816みのおエフエムさん が取材に来てくれました。
【情報】
箕面市立青少年教学の森 野外活動センター
箕面市の教学の森 野外活動センターのページはこちら
食事は原則として材料持込の自炊になります。
普通のメニューに必要な炊具は、すべて揃っており無料で貸し出してくれます。
(皿・コップ・箸・スプーンなどの個人用食器は持参して下さい)
なお、20名以上の場合には、食材及び簡易給食の斡旋が可能です。
今回の場所の利用料金
箕面市内 日帰り利用で、大人 100円 小人 50円
〒562-0005
大阪府箕面市新稲2-257-3
TEL:072-722-8110
FAX:072-722-5766
阪急「箕面」駅より徒歩 約2.5km
阪急「池田」駅より阪急バス乗車「東畑」駅下車徒歩 約1.3km
北大阪急行「千里中央」より阪急バス乗車「新稲」駅下車徒歩 約1.1km
そのときに、パパにもぜひにって、参加してもらったほうが、うまくいきます。やっぱり外ではパパの出番が多くなりますからね。
パパにも育児の話や、趣味の話が出来るパパ友達をつくるチャンスだし、みんなで分担すれば、家族の中でパパだけが働きっぱなし(!)にもならなくて済むのでは?
料理は何でもいいけれど、簡単で、子どもたちも料理に参加しやすいカレーライスとバーベキューにしました。どちらも王道ですよね。
なぜ、どちらも?と思われた方もおられるのではないでしょうか。はい、どちらかでもいいのですが、カレーは子ども受けがよく、バーベキューは大人受けがいいからです。まずは、カレーライスを作ってしまって、子供たちは基本的にはカレーライスが昼食です。あとから、ゆっくりバーベキューをしても、充分です。

今回は、洗ったお米とカレーの具材、バーベキューの具材を、各家庭分は各自で持ち寄りで、
カレールウ(甘口を用意しました)や、この甘口のカレーに、大人向けの辛さにできるスパイス(食べるときに入れる)と、バーベキュー用の焼肉たれなどは、まとめて購入しました。
最初は、自分の子どもに教えていましたが、自然とだんだん他の子に教えてたりします。一緒のことをみんなでする醍醐味ですね。


カレーとは言えど、具材の打ち合わせもなく、お楽しみのごった煮です。お肉も牛だったり、チキンだったり、豚肉だったり・・・。
でもでも、とっても、おいしかったんです。
みんなすごくおかわりして、まずご飯がなくなった!!子どもたちよく食べる、食べる。
ルウはさらっとした食感で、マイルドな味だったし、大人はカレースープとして飲んでたりもしました。

コツは、早く火が通るように、野菜もお肉もいつもよりずっとずっと細かく切ること。
これで、具材が固い!というよくありがちなことは、防げました。また、今回のように、カレールウがあまった場合に持って帰れるように、ファスナーつきジップロックを用意してると、ご飯も野菜でもなんでも捨てなくて済みます。
この場所を選んだのは、近いからだけではなく、キャンプカウンセラーのお兄さんやお姉さんが、いてくれるからです。
道具の準備、火の起こし方、飯ごう炊飯の仕方、など、わからないことは教えてくださるので、頼もしいです。また、子どもたちが午後から連れて行ってもらったグリーンハイキングは、きのこや虫をみつけたり、クイズをしてもらったり、とっても楽しかったそうです。
また、ベビー連れだったのですが、木陰がありますし、思ったより快適にベビーカーで寝ていました。
これから秋まで、楽しめると思いますので、ぜひトライしてみてくださいね。
この日は、みっけ!みのおの子連れアウトドアの様子を
タッキー816みのおエフエムさん が取材に来てくれました。
【情報】
箕面市立青少年教学の森 野外活動センター
箕面市の教学の森 野外活動センターのページはこちら
食事は原則として材料持込の自炊になります。
普通のメニューに必要な炊具は、すべて揃っており無料で貸し出してくれます。
(皿・コップ・箸・スプーンなどの個人用食器は持参して下さい)
なお、20名以上の場合には、食材及び簡易給食の斡旋が可能です。
今回の場所の利用料金
箕面市内 日帰り利用で、大人 100円 小人 50円
〒562-0005
大阪府箕面市新稲2-257-3
TEL:072-722-8110
FAX:072-722-5766
阪急「箕面」駅より徒歩 約2.5km
阪急「池田」駅より阪急バス乗車「東畑」駅下車徒歩 約1.3km
北大阪急行「千里中央」より阪急バス乗車「新稲」駅下車徒歩 約1.1km
2009年07月20日
虫と仲良くなろう!みのお・瀧道四季のまつり2009 その2

みのお・瀧道夏まつりイベント「虫と仲良くなろう!」のくるびーと行く『キリギリス探し』に参加し、箕面周辺へキリギリスを捕まえに行きました。
当日は、午後は大雨との予報でしたが、午前中はうす曇で、少し涼しくて出かけやすいくらいでした。
大阪青山短期大学ちかくのところへ案内してもらい、いざ、キリギリス探し。
昨日の虫の話のイベントの時に、キリギリスを見せてもらい、根っからの箕面人なのにキリギリスを見たのは初めてだったのと、すごく近くで観察させてもらって、色のきれいさに惚れ惚れしてしまって、ついつい夢中に・・・。正直、私、虫きらい(虫が怖い)だったのに、不思議なくらいです。観察って大事なんですね・・・。
今回の目的は、『虫の音の聞こえる瀧道』
箕面らしく皆様に楽しんでもらえる瀧道づくりの一環として、捕まえたキリギリスを瀧道のお店にもわけて、夏休み期間中、みんなに楽しんでもらおうというもの。
キリギリスは、オスだけが鳴きます。ですから、鳴くオスだけを目標に、メスは繁殖してもらうため捕まえても、逃がすお約束で、子どもたちも一生懸命探してました。キリギリスのオスとメスの違いは、お尻のところにあります。メスは長い尿管がついているので、一目瞭然です。
キリギリスは、警戒心が強いらしく、私たちが入っていく草むらでは、キリギリスが鳴いてない・・・。(許可をもらってるところ)しかし、すぐ近くの畑とか私有地ではしっかり鳴いているってことは、いるはず!と、皆さん必死でした。
草むらには、バッタやコオロギ、ヒメギス(キリギリスの仲間)など、他にも虫がたくさんいました。最近見る機会が少なくなってきた大きなシオカラトンボもいて、虫捕りを楽しみました。
他にも、私個人的に長年見ていないアマガエルを久しぶりに捕まえたり、カナヘビ、ヤモリなどもいましたよ。

実は、小学生のアンケートで、虫が嫌いと答えた子の理由に、お母さんが嫌いだからと言う答えが非常に多いそうです。
私自身、子供たちにそんな理由で、嫌いになってほしくないし、案外虫が好きな子供たちに少しずつ慣れさせられてるような気がします。
飼育すると、少しずつ触れる機会が増えます。なぜなら、子どもたちだけではお世話が出来ないから。そして、なんだか愛着がわいてきて、そうしてすこしずつ、家で飼育する生き物が増えてる我が家です。
子どもたちには、生き物や命、小さいものを大事にする気持ちが育ってほしいと思っています。
ちなみに・・・
現在、飼育中なのは、
カタツムリの赤ちゃん・・・かなり小さいから平気、ボンヌママンのジャムのビンで飼育。
ミナミヌマエビ・・・魚に興味はないが、エビが好きな私がもらってきました。
元は箕面川に住んでいたもの。 これまた小さい。
産まれたての赤ちゃんの小さくても体が完成して産まれている様子には、
感動します。素敵な花瓶(うちには高価!)で、水道水で飼育。
暑い時期は、氷いれて温度調整しています。
でないと、実際、半日ほど家を留守にすると、
大きい個体から順番にゆであがって死んじゃいます。
カブトムシ オス1匹、メス2匹・・・ムスメがもらったもの。
そして今回のキリギリス、バッタ。
もう、増やさないよ!が、最近の口癖です。
【情報】
くるびーと行く『キリギリス探し』
箕面周辺へキリギリスを捕まえに行きます。
日時: 7/19(日) 10:00~12:30解散予定
集合: 箕面文化・交流センター 地下1階 フリースペース
参加費: 100円(保健代)
持ち物: 軍手・虫捕り網・帽子・水筒
※雨天順延 7/20(月・祝)
【申込み】 072-724-5151(箕面わいわい株式会社)
※先着30名 小学生以上(低学年は保護者同伴)
主催: みのお本町会 / 箕面物産商組合 / 箕面都市開発株式会社 / 箕面文化・交流センター
協力: 箕面公園昆虫館
2009年07月20日
虫と仲良くなろう!みのお・瀧道四季のまつり2009に参加して

みのお・瀧道 四季のまつり 2009のイベント、箕面公園昆虫館 館長のくるびーさんの『昆虫の不思議な話』を聞きに、行ってきました。
昆虫の幼虫と成虫の違いのお話を聞きました。さて、幼虫と成虫の違いとは?
成虫は、
・羽化 はねを持っている。基本は4枚。
・大きくならない。 小さい。
・6本足
成虫になっても羽のない虫・・・アリ、ナナフシ、サツマゴキブリ、アタマジラミ、ネコノミ、など。
また、蜂は2つの複眼を持っていますが、実はその間に単眼とよばれる3つの目を持っているそうです。眼が、5つもあるなんて、びっくり!
くるびーさんは、「近畿には3つの昆虫館しかなく、そのうちの1つが大阪府営箕面公園昆虫館なので、箕面の人は恵まれています。中学生まで入館料は無料なので、ぜひ親子でいっぱい足を運んでください。」とおっしゃられてました。
※3つの昆虫館・・・大阪の箕面公園昆虫館、奈良の橿原市昆虫館、兵庫の伊丹市昆虫館。
6月4日~9月30日 近畿にある昆虫館の合同企画、 『昆虫館スタンプラリー2009』が行われています。
箕面・橿原・伊丹のきんき昆虫館3館をめぐってスタンプを集めると、人気のコーカサスオオカブト・ヘラクレスオオカブト・ギラファノコギリクワガタがデザインされたオリジナルバンダナがもらえるので、ぜひ夏休みにトライしてみてはいかがでしょうか。
▽対象:3歳以上
▽内容:近畿地方にある3つの昆虫館に入館し、スタンプを集めよう!3館達成すれば、オリジナルバンダナをプレゼント。
*景品が無くなり次第終了します。
そして、大阪府立狭山池博物館で、世界の昆虫展(7/25~8/30まで)が開催されており、箕面公園昆虫館で所蔵しているものが展示されています。とのこと。また、狭山池のバタフライガーデンは、チョウなどの昆虫を観察ができます。
8月9日(日)・23日(日)には大阪府営箕面公園昆虫館館長の久留飛克明氏による昆虫についての楽しいお話があります。
くわしくは、大阪府立狭山池博物館ホームページまで。
さて、続いて、お話の後の2つ目のイベント、箕面の竹で『虫かごを作る』にも飛び込み参加させて頂きました。こちらは、福西おじさんに教わって、箕面の山でとれた竹を使って、虫かごを作ります。
こちらのキット、全部福西さんのお手製。今回の30組の参加者のために、1ヶ月以上費やして、作成してくださったそう。竹は丈夫ですから、結構手が切れることもあったそうです。
なるほど、完成のお見本には、キリギリスが入って、とっても素敵。(このページTOPの写真)作るほうも、早く完成させたいと意欲が湧き上がります。

型紙に合わせて各パーツを、側面大2面、小1面を組み立てていきます。

その後、福西さんの作ってくださっている
虫の出入り口のある面と合わせて、周り4面を組み立てます。
それが、出来たら、底面・上面を竹ひごで組み立てて、ほぼ完成です。

一見、組み立て方は難しくないのですが、竹ひごを入れていく作業は、大人でも固く、時々竹ひごが刺さり、痛かったです。小1のムスメは、よくがんばったなと思いました。
そして、途中、同じ会場でタッキーみのお816の生放送があり、イベントの様子も放送されました。みのお・瀧道 四季のまつり 2009主催者でもあります箕面わいわい株式会社のYさんと一緒にムスメも出演させていただきました。
最後に出ている竹ひごの先を切ったり、やすりで仕上げを福西さんがしてくださって、完成となりました。
【情報】
虫と仲良くなろう!
くるびーの『昆虫の不思議な話』
学校では教えてくれない、昆虫のお話。 ※チラシはこちらをご覧ください
日時: 7/18(土) 10:00~10:30
会場: 箕面文化・交流センター 地下1階 フリースペース
参加費: 無料
主催: みのお本町会 / 箕面物産商組合 / 箕面都市開発株式会社 / 箕面文化・交流センター
協力: 箕面公園昆虫館
箕面の竹で『虫かごを作る』
箕面の山でとれた竹を使って、虫かごを作ります。
日時: 7/18(土) 10:40~12:30
集合: 箕面文化・交流センター 地下1階 フリースペース
参加費: 500円
【申込み】 072-724-5151 (箕面わいわい株式会社) ※先着30名 小学生以上(低学年は保護者同伴)
主催: みのお本町会/箕面物産商組合 / 箕面都市開発株式会社 / 箕面文化・交流センター
協力: 箕面だんだんクラブ
2009年07月05日
夏の里山体験で、深緑を味わう
箕面森町とどろみの森クラブ主催の夏の里山体験に行ってきました。
とどろみの森クラブのクラブハウスに到着。
クラブハウスの中はこんな感じ。
周辺は、山、川、棚田と自然に囲まれています。川には、魚はもちろん、蟹、エビが生息しています。
山では、カブトムシが生息しています。
この小屋では、280匹も幼虫がいるのだとか!
こちらは、もうすぐ成虫になるカブトムシのさなぎ。オスです。
午前中は、畑に出来た農作物の収穫体験。
大量に取れた玉ねぎ、ジャガイモ(メークインと男爵)の大きさにびっくり!
収穫後、みんなですぐに試食してみました。
玉ねぎは、まずはそのまま、オニオンスライスで。
オニオンスライスは、水にさらさず、(65%の栄養が流れてしまうとか・・・・)本当にそのままなので、最初は玉ねぎの甘みが感じられますが、後から辛味が感じられます。しかし、わしわし食べるわが娘。普段、「辛い~。」と言って、食べれないのが、信じられないくらいです。
その後、鍋で蒸した玉ねぎもいただきました。
これまた、さっき食べた生ともひと味違って、少し入れたバターの味付けがおいしい!
お酒のあてにもよさそうです。
ジャガイモはダッチオーブンに入れて、ベークドポテトに。
素材そのものの味がおいしくて、大満足でした。
その他、とどろみの森クラブの方たちに作ってもらった、スモークエッグ(燻製卵)も、参加者に人気でした。
午後からは、七夕の由来を教えてもらって、飾りつくり。ちょうちんや金魚、あみ飾り、織姫と彦星、お星さまなどなど。
3歳のムスコは、わっかかざりや、さんかくつづり、ひし形つづりの飾りをつくってました。
(家族一丸となって(?)熱中していた為、写真撮り忘れました・・・。)
参加者は、希望のサイズの笹をもらい、短冊と共につけました。
(うちは、ムスメが欲張って、とっても大きな笹をいただきましたので、自宅に帰ってから天井をほとんど覆う大作に・・・

 、
、でもとっても季節感のある部屋になり、いいものを作らせてもらいました。
 )
)畑の周りでは、バッタや昆虫がたくさんいて、子どもたちは虫取りも楽しんでました。
はじめて会った子と遊べるのは、子どものよいところですね~。
【情報】
・七夕飾り作り
・農作物の収穫と試食等
開催日 7月5日(日) 10:00~15:00
クラブハウス周辺


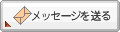
 大阪ブログポータル オオサカジン
大阪ブログポータル オオサカジン





